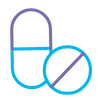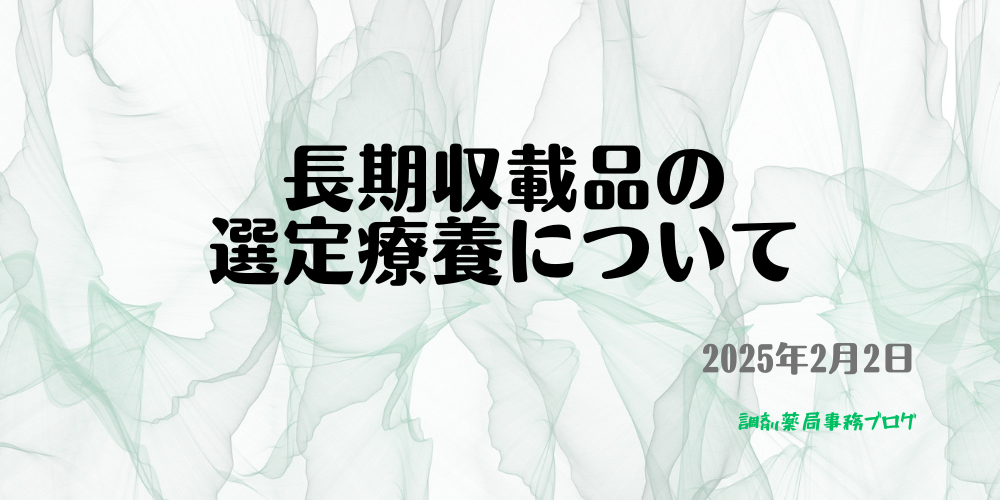
どうも!あんでぃです。
本日は2024年10月より始まった長期収載品の選定療養についてまとめてみました。医療上の必要性がなく長期収載品を選択した場合の患者負担が大きくなりました。
長期収載品とは
長期収載品とは、特許期間が満了し、後発医薬品が発売されている医療用医薬品のことです。品質や信頼性の面で一定の支持を得ています。しかし、ジェネリック医薬品と比較すると価格が高いです。
自分の飲んでいる薬が該当する長期収載品なのか気になる方はお薬をもらっている薬局等で確認すればすぐに教えてくれますよ。
選定療養の目的
選定療養は、医療費抑制や適正な医薬品利用を促進するための仕組みになります。長期収載品が対象となる選定療養の目的は以下の通りです。
- 医療費の適正化:ジェネリック医薬品を積極的に活用することで、医療費を削減する。
- 患者負担の軽減:ジェネリック医薬品を選ぶことで、患者の経済的負担を軽減する。
- 市場競争の促進:長期収載品とジェネリック医薬品の間で適切な競争を促進し、医薬品の品質向上を図る。
選定療養の仕組み
長期収載品が選定療養の対象となった場合、患者がその医薬品を選ぶ際には追加で自己負担が発生します。この仕組みによって、患者はジェネリック医薬品の利用を検討する機会を得られる一方、医療機関や薬局は患者の選択を尊重することが求められます。
具体的には以下の手順で進められます。
- 対象医薬品の選定:厚生労働省や関連機関が、長期収載品の中から選定療養の対象となる医薬品を決定します。
- 情報提供:医療機関や薬局が患者に対し、ジェネリック医薬品の有無や価格差を説明します。
- 患者の選択:患者が長期収載品を選択する場合、追加の自己負担が発生します。
追加の自己負担について
患者の診療に係る費用は、大きく次の(1)及び(2)の合計から構成されています。
(1)選定療養による「特別の料金」となる費用(長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1に相当する費用)
(2)選定療養を除く保険対象となる費用(保険外併用療養費と患者自己負担の合計額)
選定療養の計算方法
- 「特別の料金」の計算
- 価格差:長期収載品(先発医薬品)と後発医薬品(ジェネリック)の価格差を求めます。
- 価格差の4分の1:求めた価格差を4で割ります。
- 数量調整:投与量や日数に応じて計算します。
- 消費税加算: 計算した金額に消費税(10%)を加えます。
- 保険適用部分の計算
- 保険適用価格:長期収載品の価格から、価格差の4分の1を差し引いた額。
- 患者の自己負担: 保険適用部分の価格に自己負担割合(例: 30%)を乗じて算出します。
- 患者の総負担額
- 「特別の料金」と「保険適用部分」の自己負担額を合計します。
上記の計算方法はとてもシンプルにまとめたものになりますので、詳しく知りたい方は厚生労働省のホームページをご覧ください。
実際の金額が気になる方はお薬をもらっている薬局で計算できますので、お気軽に相談してみてください。
選定療養のメリットと課題
メリット
- 医療費の削減:ジェネリック医薬品の普及により、国全体の医療費を抑制できる。
- 患者の選択肢拡大:患者がコストと品質を考慮して医薬品を選べる。
- 製薬業界の活性化:ジェネリックメーカーとオリジナルメーカーの競争が促進される。
課題
- 情報不足:患者がジェネリック医薬品の品質や効果について十分な情報を得られない場合がある。
- 医療機関の対応負担:医師や薬剤師が患者への説明に時間を割く必要があり、業務負担が増える可能性。
- 追加負担の公平性:経済的理由で長期収載品を選びたくても選べない患者が出る可能性。
今後の展望
長期収載品の選定療養は、日本の医療制度の持続可能性を高めるための重要な取り組みです。しかし、患者が安心してジェネリック医薬品を選択できる環境を整えることが、さらなる普及の鍵となります。政府や医療機関、製薬業界が連携し、情報提供や啓発活動を強化することが求められています。
選定療養がもたらす変化を正しく理解し、患者にとって最善の選択ができるよう、私たちも積極的に情報を共有していきましょう。
ご不明点やご質問などがありましたらコメント、お問い合わせからお願いします。
その他、まとめてほしい内容や加算、薬局のことなど記事にしてほしい内容がありましたらお気軽にご連絡してください。
皆さんと調剤事務員としてステップアップできればと思います。